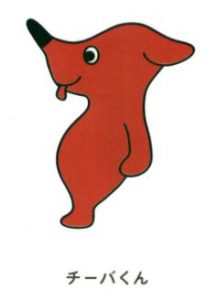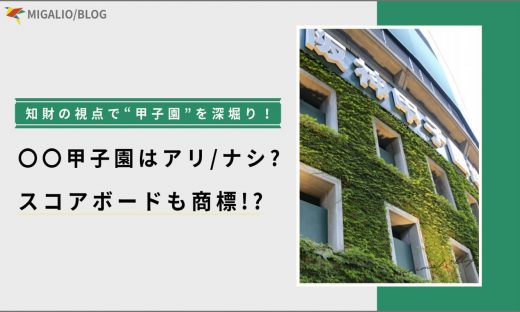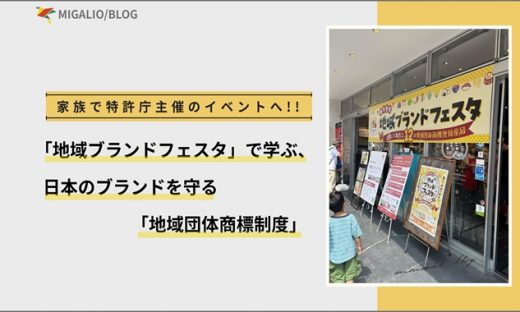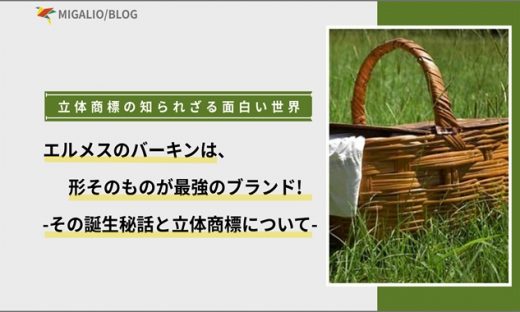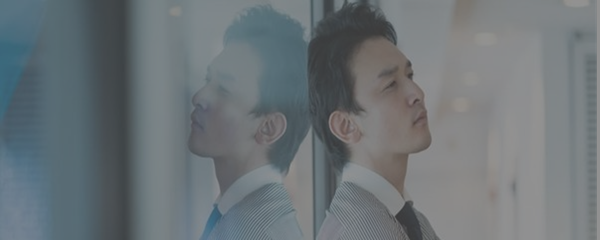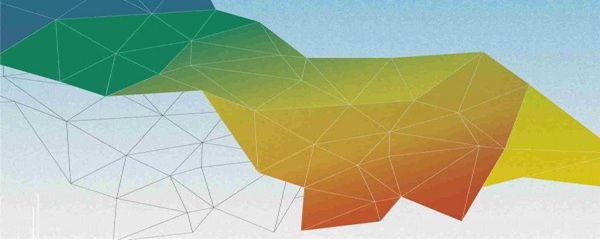Suicaのペンギン「卒業」で振り返る。作者・坂崎千春氏が手掛けたあのペンギンの人気の秘訣と「イソジンファミリー」誕生の裏側
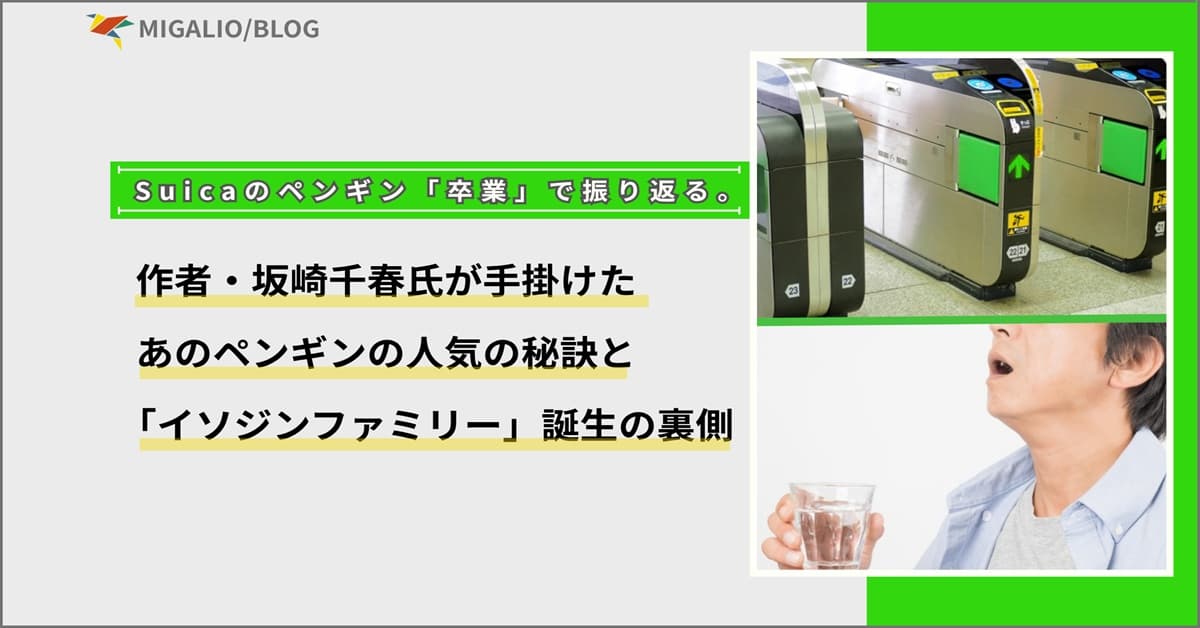
2025年11月、Suica®のペンギンが2026年度末をもって「卒業」するという衝撃的なニュースが発表されました。多くの人が「当たり前の存在」として親しんできたキャラクターの交代劇は、SNSでも大きな話題となっています。
⇒⇒「Suicaのペンギン、卒業へ 26年度末で新たなキャラクターにバトンタッチ」 IT media NEWS
しかし、この出来事を単なる「キャラクターの引退」として見るだけでは、その裏側にある企業戦略と知財の重要な側面を見過ごしてしまうかもしれません。
実は、このペンギンの作者である坂崎千春さんは、かつて「カバくん®」との権利分離で揺れた「イソジン®」の新キャラクターも手掛けています。この2つの国民的ブランドには、それぞれ全く異なる知財の背景(エピソード)がありました。
この記事では、Suica®ペンギンの卒業理由を「権利の視点」から推察すると共に、イソジンファミリー誕生の過去を振り返り、キャラクタービジネスの裏側にある知財のエピソードを紐解いていきます。
記事の目次
記事内容のスライドを無料配布中!
社内報での知財トピック紹介や、営業部・開発部との定例会議での情報共有など、
社内での知財への関心を高める「きっかけ」として是非ご自由ご活用ください。
※スライドはクレジット表記不要で、自由に編集・ご利用いただけます。ただし、本資料の再配布、販売、および有料セミナーでの利用など、営利を目的としたご使用はご遠慮ください。
※内容の正確性には万全を期しておりますが、ご利用の際は再度ご確認をお願いいたします。
【衝撃】Suicaペンギン、2026年度末での「卒業」を発表
2025年11月11日、鉄道系ICカードの先駆けである「Suica®」に関して、衝撃的なニュースが発表されました。Suica誕生25周年という節目にあたる2026年度末をもって、あの「Suicaのペンギン」が、公式キャラクターを「卒業」するというのです。
この発表を受け、SNSでは「悲しすぎる」「あのペンギンだからSuicaを使っていたのに」といった驚きや感謝の声が溢れ、一部では「卒業撤回」を求める署名活動も始まっているようです。
JR東日本によれば、コード決済の導入など「新しい次元へ進化するSuica」のイメージを刷新するため、新キャラクターへのバトンタッチを決定したとのこと。2001年のSuica登場以来、約25年間にわたり「当たり前」の存在だったキャラクターの卒業は、大きな注目を集めています。
作者・坂崎千春さんとは?
「Suicaのペンギン」の生みの親は、絵本作家・イラストレーターの坂崎千春(さかざき ちはる)さんです。
坂崎さんは、Suicaペンギンの他にも、千葉県のPRマスコットキャラクター「チーバくん®」など、数多くの有名なキャラクターを手掛けています。そして実は、彼女は「イソジン®」の現行キャラクターである「イソジンファミリー」の作者でもあるのです。
「イソジン®のファミリーは、イソママ、イソパパ、イソくんの三匹のワンちゃんファミリー。バイ菌やウィルスから、日本の家庭を守ってくれています。」
(坂崎千春さん公式HPより引用)
商標登録第5073663号 「チーバくん」
Suicaペンギンの作者・坂崎千春さんは、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」のデザインも手掛けています。
【J-platPat リンク】https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2007-003301/40/ja
【知財エピソード①】Suicaペンギンの「権利」と「卒業の理由の推察」
なぜ、これほど愛されているキャラクターを卒業させる必要があるのでしょうか? そのヒントは、Suicaペンギンの「出自」と「権利関係」に隠されているかもしれません。
「オリジナル」ではなかった? Suicaペンギンの出自
多くの方は、あのペンギンはSuicaのサービス開始時にJR東日本が依頼して作られた「オリジナルキャラクター」だと思っているかもしれません。
しかし、実際は坂崎さんの既存の絵本『ペンギンゴコロ』(1998年発行)に登場するキャラクターを「起用」したものなのです。Suicaペンギンの著作権表記の先頭がJR東日本ではなく坂崎さんになっているのはこのためです。
つまり、JR東日本は「自社で権利を100%持つキャラクター」を使っていたわけではなく、あくまで「作家さんの作品をライセンス契約し、共に良好な関係を築きつつ二人三脚でSuicaブランドを広め、展開していた」状態だったと言えます。
参考:「Suicaのペンギンはこうして生まれた (前編)」 電通報
「Suicaのペンギンはこうして生まれた (後編)」 電通報
なぜこれほど愛された? ペンギンの「人気の秘訣」
Suicaのペンギンがこれほど長く愛され、定着した理由は何だったのでしょうか。その秘訣は徹底した「設定のなさ」なのではないかと言われています。⇒「なぜSuicaのペンギンは愛されるのか ペンギンの顔をした「ベレー帽」が“激アツ”の理由」 IT media NEWS
- あえて名前をつけない(ICカードの分身)
「Suicaのペンギン」には固有名詞がありません。これはJR東日本が意図したもので、「特定のキャラ(タレント)」ではなく、あくまで「Suicaというカードの分身」であるという位置づけを徹底したためです。 - 「余白」が想像力をかき立てる
「南極から来た」「好物は魚肉ソーセージ」程度の緩い設定はありますが、細かい性格付けはされていません。この「情報の少なさ」が、モンチッチのように「持ち主が自由に性格や物語を想像できる余白」を生み、親近感を高めました。 - 「ハウス・キャラクター」としての成功
独立した人気者(フェイマス・キャラクター)を目指すのではなく、常にブランド(Suica)に寄り添う「ハウス・キャラクター」に徹しました。これにより、Suicaの普及と共に自然と生活に溶け込み、単なるブームで終わらない長寿キャラとなりました。
【推察】なぜ今「卒業」なのか? ビジネス視点の3つの理由
ここからはあくまで推測になりますが、著作権が「企業」ではなく「作家」にあるというこの構造が、今回の決断に影響を与えた可能性は否定できないのではないかと考えています。
デジタル展開の「自由度」を確保したい
今後、Suicaは「Suica Renaissance」の第二弾として、Suicaを「移動と少額決済のデバイス」から「生活のデバイス」へと進化させることを打ち出しています。「コード決済」や「個人間送金」を導入し、機能追加やUI改善が頻繁に行われるこうしたデジタル領域では、デザインの変更やアプリ内での展開のたびに「監修(許諾)」が必要な体制は、スピード感の足かせになりかねません。自社権利のキャラクターに切り替えることで、この確認コストをなくし、変化の激しいデジタル決済市場で柔軟かつ迅速に展開したいという狙いがあるかもしれません。
権利のコントロールとコストの最適化
25年という長期にわたり人気キャラクターを維持するには、相応のライセンス料が発生しているはずです。経営効率を考えた際、外部のIP(知的財産)を利用し続けるよりも、自社で完全にコントロールできる資産(新キャラクター)に投資を切り替えるタイミングだったとも考えられます。
「権利継承」のリスクマネジメント
非常にデリケートな話ですが、企業にとって「属人性」はリスクになります。もし将来、作者に万が一のことがあった場合、著作権(著作財産権)は相続人のご家族などに相続されます。過去には、作者の死後に権利関係が複雑化し、キャラクターが使えなくなるトラブルも数多く起きています。
作者である坂崎さんと良好な関係である今のうちに、「25周年」という花道を作って卒業することは、企業としても作家へのリスペクトとしても、最も安全な「出口戦略」だったのではないでしょうか。
【補足】「著作権」と「商標権」はどう違う?
「著作権」と「商標権」は、キャラクタービジネスを考える上で基本的なポイントです。ここで簡単に整理しておきましょう。
① 著作権(作者の権利)
- 権利の発生:作品を創作した瞬間に自動で発生します(特許庁などへの登録は不要)。
- 保護期間:原則として作者の死後70年まで。
- Suicaの場合:作者の坂崎さんに帰属しています。
② 商標権(ビジネスの権利)
- 権利の発生:特許庁に「出願」し、「登録」されて初めて発生します。
- 保護期間:登録から10年ですが、更新手続きをすれば半永久的に保持できます。
- Suicaの場合:「Suica」という名称はJR東日本の商標ですが、ペンギンのキャラクターの商標は当然ありません。
この「著作権」と「商標権」の区別が、次のイソジンのケースで極めて重要になります。
●著作権や商標権に関しては、以前の記事でも登場しているので是非覗いてみてください。
【知財エピソード②】イソジンファミリー「誕生の背景」
さて、先ほど坂崎さんは「イソジンファミリー」も手掛けていると書きましたが、多くの方がこう思ったのではないでしょうか。
「あれ? イソジンといえば、あの『カバくん』では?なんで犬のファミリーなの??」
そう!まさにその「カバくん®」こそが、犬のイソジンファミリー誕生の背景にある、もう一つの知財エピソードの鍵を握っています。
権利分離と、明治の「カバくん」商標戦略
なぜ「カバ」が消え、「犬」になったのか。その背景には、半世紀以上にわたる歴史と、提携解消に伴う激しい「権利の攻防」がありました。
2016年3月まで、「イソジン®」ブランドのうがい薬は、オランダのMundipharma B.V.(ムンディファーマ、現:iNova Pharmaceuticals Japan株式会社)が「商標権」を保有し、提携した明治グループ傘下のMeiji Seika ファルマが製造販売承認を得て販売していました。その歴史は古く昭和の時代から『カバくんのイソジンうがい薬』として、カバのキャラクターは消費者に完全に定着していました。
ところが2015年、両社の提携が解消されることになると、事態は急変します。
「イソジン」の商標(商標登録第584989号)を持つムンディファーマ側との契約が終了したため、明治側は『イソジン』という名称が使えなくなりました。しかし、明治には切り札がありました。実は明治側は、キャラクターである「カバくん」の商標(商標登録第5627660号)をしっかりと取得していたのです。
そこで明治は、『イソジン』の名前が使えない代わりに、築き上げてきた「カバくん」ブランドで勝負するという戦略に出ました。
その対応は極めて迅速でした。提携解消のリリースが出たのが2015年12月9日。(イソジン®製品に関するムンディファーマへの製造販売承認移管のお知らせ)そのわずか5日後の12月14日には、関連する「カバくんのうがい薬」(商標登録第5861881号)の商標を出願しています。このスピード感からも、明治がいかにこのブランド防衛に本気だったかがうかがえます。
【解説】起きてしまった「権利のねじれ」の状態とは?
本来セットで認識されていた「商品名」と「キャラクター」の権利が、提携解消によって真っ二つに分かれてしまった状態です。
- 商品名(イソジン):商標権を持つムンディファーマ(iNova社)へ戻る
- キャラ(カバくん):明治が独自に商標登録していたため、明治の手元に残る。さらに「カバくんのうがい薬®」の商標も取得し、権利を強固にしていた
これにより、市場には「カバくんのいないイソジン」と「イソジンと名乗れないカバくん(明治うがい薬)」が同時に並ぶという、消費者にとって非常にややこしい状況が生まれました。
一方、本家『イソジン』側(当時のムンディファーマ社等)も黙ってはいませんでした。彼らは日本での販売パートナーをシオノギヘルスケアに変更し、新たなパッケージで『イソジン』を販売しようとしました。しかし、その新パッケージには、「カバくん」によく似たキャラクターが描かれていたのです。
これに対し、明治側が反発。「長年親しまれてきたカバくんに酷似しており、お客さんが混同してしまう」として、不正競争防止法に基づき、イソジン側に対して類似キャラクターの使用差止を求める仮処分命令申立を行ったのです。
つまり、カバくんを守るために法的なアクションを起こしたのは、商標権を持つ明治側だったのです。
- ~2016年3月
蜜月時代と「カバくん」の定着明治グループがMundipharma社と提携し、「イソジン」を製造・販売。昭和の時代から「カバくん」はイソジンの顔として親しまれていました。
- 2015年:提携解消
明治の戦略的商標確保提携終了により、明治は「イソジン」の名称が使用不可に。そこで明治は、「イソジン」の代わりに「カバくん」の商標を確保し、「明治うがい薬」として販売を継続する道を選びます。
- 騒動:類似キャラ問題
イソジン側の動き一方、本家「イソジン」側(ムンディファーマ・シオノギ)は、新パッケージに「カバくん」によく似たキャラクターを描いて販売しようとしました。
- 法的措置:差止請求
明治の反撃これに対し明治側が猛反発。不正競争防止法に基づき、使用差止を求める仮処分を申し立てました。
「和解」と、商標登録された「イソジンファミリー」
最終的に両社は和解。イソジン側(iNova/シオノギ等)は、カバくんの使用や類似デザインを避け、完全に新しいキャラクターを起用する道を選びました。
そこで白羽の矢が立ったのが、Suicaペンギンの作者である坂崎千春さんだったのです。こうして犬の「イソジンファミリー」が誕生しました。
注目すべきは、イソジン側がこの教訓を活かし、新しいキャラクター「イソママ」「イソパパ」「イソくん」を、しっかりと自社で「商標登録」している点です。
商標登録第5931127号 「イソママ」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-070716/40/ja
商標登録第5974541号 「イソパパ」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-029958/40/ja
商標登録第5974542号 「イソくん」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-029959/40/ja
Suicaペンギンが「作家と契約して起用していた(商標登録なし)」のに対し、イソジンファミリーは「トラブルを経て、権利を強固にするために生まれた」という、対照的な背景が見えてきます。
【コラム】カバくんが使われているうがい薬は今はどこが製造・販売しているの?
明治が死守した「カバくん」ですが、実は現在、明治の手を離れていることをご存知でしょうか。
2022年11月、健栄製薬(けんえいせいやく)という会社が、「明治うがい薬」の製造販売承認を承継しました。
実はこの健栄製薬、もともと「明治うがい薬」の製造を行っていたメーカーです。今回、明治から販売権も譲り受け、製造から販売までを自社で手掛けることになりました。商品名は『健栄うがい薬』となりましたが、『カバくん』という財産(商標権)もしっかりと引き継がれています。
最近テレビCMで、人気タレントを起用した『健栄うがい薬』のCMを見かけますが、パッケージには変わらず「カバくん」が描かれています。カバくんは、明治から健栄製薬へと移籍し、今も元気に活躍しているのです。
まとめ:キャラクタービジネスと知財の多様性
Suicaペンギンの「卒業」というニュースをきっかけに、キャラクターの裏側にある知財のエピソードをご紹介しました。
Suicaのように「作家の既存作品を起用して、共に愛されるブランドを育てる」戦略もあれば、イソジンのように「権利トラブルを教訓に、自社で完全に権利を保有する」ケースもあります。
今回のSuicaペンギンの卒業は、ファンとしては寂しい限りですが、ビジネスの視点で見れば「権利関係を整理し、次の25年を見据えた自立への一歩」と捉えることができるかもしれません。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。