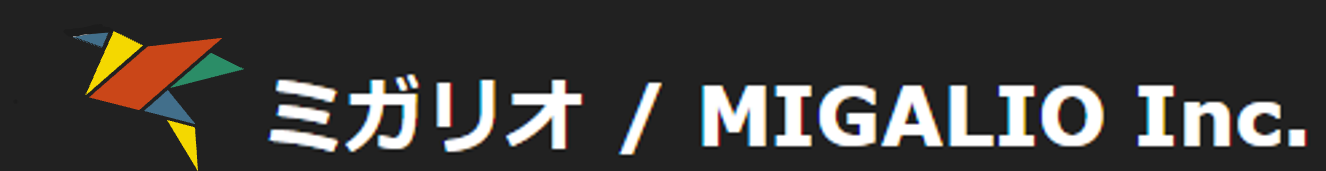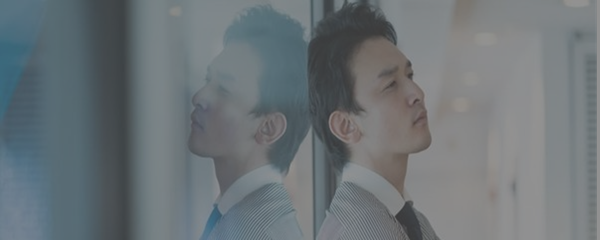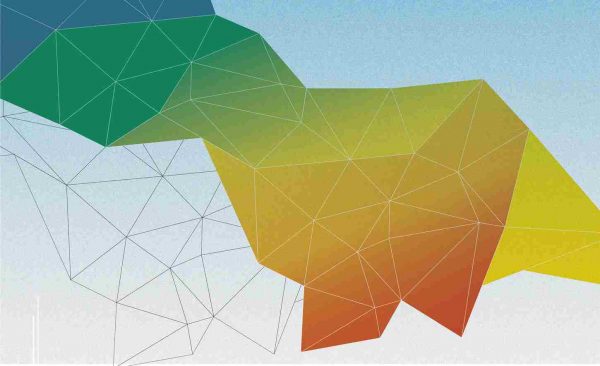商標出願における「称呼」の重要性と二段書きの活用法
商標出願するときは、同じような商標がないかを調査して他の商標出願と差別化して出願しないと
権利化できないことは知っていましたが、具体的に、どういう場合に
「同じような商標」と見做されてしまうのかはよくわかりませんでした。
今回、せっかく調べたので備忘録として書いておきます。
なお、出願する商標が造語の場合に限定しています。
商標審査における類似性判断の基準
★商標審査における「他人の登録商標との類似性判断」について、
第4条第1項第11号(出典:特許庁)によると
- 造語には「観念」(言葉の意味)がほぼなく、ロゴとするデザインを決めたわけでもなければ
「外観」に特徴もなく、「称呼」が主な審査対象となりそう。 - 「称呼」は、その商標を見て日本人が自然に認識する「音」(読み方)。
願書で指定できず、審査官が勝手に認定する。 - 称呼について、一文字分の違い位までは、類似すると判断されそう。
二段書きの活用について
★称呼を指定できるかもしれない手法として「二段書き」があります。
「二段書き」で出願すれば、意図しない称呼で評価されてしまう事態を回避でき、
類似するものなしとして登録される「かも」しれません。
ただし、二段書きで称呼を限定してくれるかは、審査官次第のようです。
ちなみに、商標「ミガリオ」も二段書きで権利化しています。