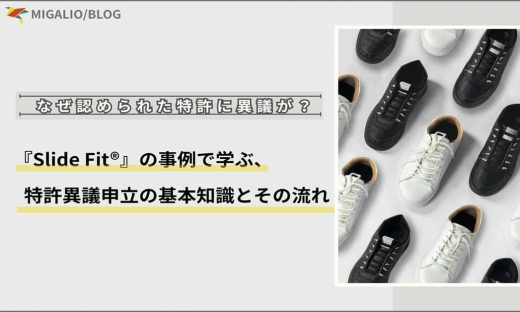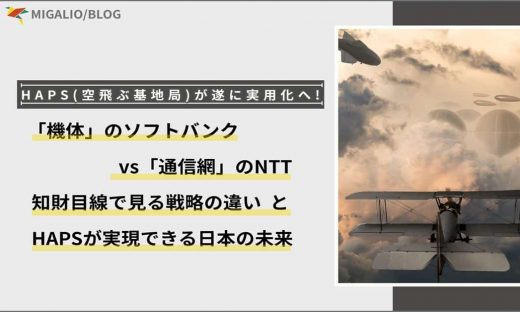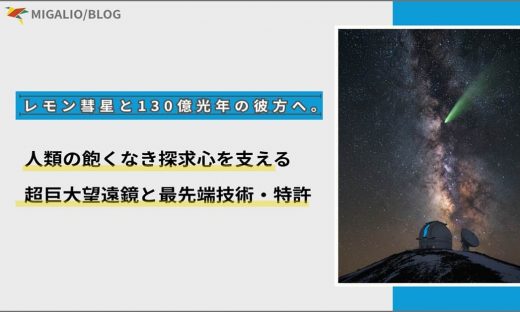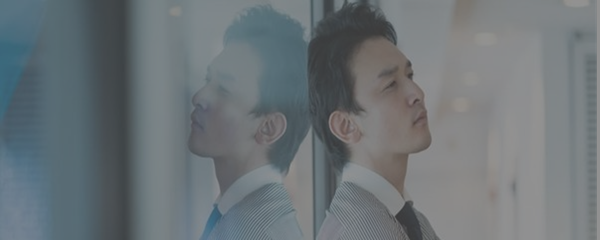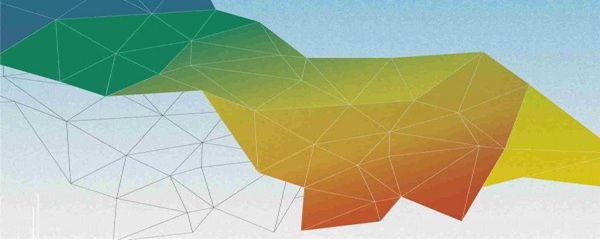【食×知財】『わさビーズ®』の出願から学ぶ、拒絶理由通知への対応と特許・ノウハウ戦略

わさびと日本人の関係は切っても切れない縁。
そして今や世界中の人にも愛される日本の誇れる食材。
わさびは日本の固有種であり、種子や苗はすべて日本に由来し、栽培をはじめたのも日本という珍しい植物です。その歴史は古く、飛鳥時代の遺跡から出土した木簡(木の手紙のようなもの)に「委佐俾三升(わさびさんしょう)」の文字があったことからわさびと日本人の歴史は約1,300年以上も前から続いています。その飛鳥時代には、税制度の租・庸・調において、地方の特産物を都に納める税としての「調」をわさびで納めることができたようです。”わさびで納税”って…想像がつかないです…
詳しくは、「日本わさび協会」さんのページを是非見てみてください!すごく興味深いです!
そんなわさびを使った商品の中でもとりわけユニークなのが、
田丸屋本店さんの人気商品『わさビーズ®』。
わさびをカプセル状にしたもので、その色は静岡県産のわさびの成分による天然の色で、
商品名のとおりキラキラかがやくビーズみたいなルックスをしています。
食材にふりかけるとかわいくおしゃれに「映え」ます。ただ、そのかわいくておしゃれな見た目と
裏腹に味はしっかりとわさびでツンとした辛さと爽やかな香りが鼻に抜け大変美味しいです。
(先日、燻製した笹かまにかけて食べてみましたが大変美味しかったです…!)
●株式会社田丸屋本店 さんのHPはこちら
●田丸屋本店さんの公式オンラインショップの『わさビーズ®』ページはこちら
そして、私はふと思いました。
「この製品どうやって作っているんだ?」「もしや、特許を取っているのでは?」
と思い調べてみたところ、やはり特許を取得しておりました!!
→→→ わさびビーズの製造方法 ←←←
※発明の名前をクリックすると、J-Platpatの情報にアクセスできます。
今回はこの『わさビーズ』の特許出願事例を題材に、
企業が特許を取得するまでのリアルなプロセス、特に審査段階で直面する「拒絶理由通知」への対応について自身で学んだ部分も含めて記事にしていこうと思います。
1. 出願内容の概要:「モノ」と「方法」の二本柱
まず、どのような内容で特許を求めたのかを出願書類を見てみましょう。
当初、権利として主張されたのは主に以下の2点でした。
●「モノ」の発明:
わさび抽出油が透明なカプセルに包含された「わさビーズ」という製品そのもの。
●「方法」の発明: わさびペーストに植物油と酒精を混ぜてオイルを抽出し、
それを二重パイプでカプセル化するという、そのユニークな製造方法。
製品自体(モノ)とその製法(方法)の両方を権利化しようとするのは、特許戦略の基本形の一つですが、特許庁の審査ではそれぞれの発明が特許の条件を満たしているかを厳しくチェックします。
2. 特許庁からの「拒絶理由通知」
審査の結果、特許庁から「拒絶理由通知」が送られてきました。
出願された発明に特許を認められない理由(拒絶理由)が見つかったことを知らせる通知です。
特許審査において、このような通知を受け取ることは決して珍しいことではありません。
今回、特許庁が指摘した主な拒絶理由は、「製品そのもの」の新規性の欠如でした。
【特許庁の指摘の要点】
あなたが出願する以前に、新聞記事などで『わさビーズ』という類似の商品がすでに紹介されています。そのため、あなたが出願した「製品」の発明は、新しいもの(新規性がある)とは言えません。
一方で、「製造方法」の発明については、この時点では明確な拒絶理由は発見されませんでした。
3. 拒絶理由への応答:2つの選択肢
拒絶理由通知を受け取った出願人には、応答の機会が与えられます。
主な応答の選択肢は「意見書」と「手続補正書」の提出です。
●選択肢①:意見書
審判官の判断や事実認定に誤りがある場合に、
「あなたの指摘は、ここが違います」と文章で反論・説明するための書類です。
●選択肢②:手続補正書
出願書類(特に権利を主張する「特許請求の範囲」)の内容を修正するための書類です。
例えば、権利範囲を狭めたり、誤記を訂正したりします。
今回のケースでは、商品の存在を示す明確な証拠が提示されていたため、「意見書」で反論するのは困難でした。そこで出願人は、「手続補正書」を提出し、権利範囲を再設定する道を選びました。
●権利範囲の変更: 新規性がないと指摘された「製品」に関する主張(旧請求項1, 2)をすべて削除**する。
●主張の明確化: 拒絶理由がなかった「製造方法」に関する主張(旧請求項3, 4)のみを残し、
これを新たな請求項として設定する。
同時に、発明の名称を
「わさビーズおよびその製造方法」→「わさびビーズの製造方法」に修正するなど、
発明の主題が「製造方法」であることを明確にする変更も行いました。
権利化が難しい部分を放棄し、認められる可能性が高い部分に絞ったといえます。
4. 補正の結果と特許登録
この戦略的な補正の結果、特許庁が指摘した拒絶理由は解消されました。
そして最終的に、この出願は「わさびビーズの製造方法」に関する特許として、無事に登録されました。この特許登録により、他社はこのユニークな製造方法を模倣することが法的に禁止されます。
5.「作り方」の特許取得、そのメリット・デメリットとは?
さて、『わさビーズ®』の事例では、
最終的に「製造方法の特許(「方法」の発明)」という形で権利を取得しました。
この選択は、企業にとってどのような意味を持つのでしょうか。
実は、特徴的な「作り方(製法)」を開発したとき、
企業には大きく分けて2つの保護戦略があります。
それは、①特許として権利化する道と、②ノウハウとして社内に秘匿する道です。
どちらの戦略を選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリットを書いていきたいと思います。
戦略①:「製造方法の特許」を取得する道
※今回の『わさビーズ®』が選んだ道です。
【メリット】
●強力な独占排他権: 登録から最長20年間、他社がその製造方法を無断で使うことを法的に禁止できます。模倣品に対して、差し止め請求や損害賠償請求が可能です。
●模倣の牽制効果: 特許内容は公開されるため、「この作り方は特許で保護されている」と世の中に知らしめることができ、他社の安易な模倣を防ぐ効果が期待できます。
●技術力の証明と信用向上: 「特許取得済みの製法」は、企業の高い技術力を客観的に示す証となり、ブランド価値や社会的信用を高めます。
●ライセンス収入の可能性: 他社に特許技術の使用を許可(ライセンス)し、その対価としてライセンス料を得るという新たなビジネス展開も可能になります。
【デメリット】
●技術内容の公開: 特許を出願すると、その技術内容はすべて世の中に公開されます。これにより、競合他社に技術のヒントを与えてしまうリスクがあります。
●「回避発明」を誘発する可能性: 公開された技術を参考に、特許をギリギリで侵害しない「別の方法(回避技術)」を開発されてしまう可能性があります。
●コストと時間: 出願から登録、そして権利を維持するためには、継続的に費用と時間がかかります。
戦略②:「ノウハウ」として社外秘にする道
特許出願せず、社内の重要機密として厳重に管理する戦略です。
コカ・コーラの原液レシピもこれにあてはまります。
【メリット】
●技術内容が公開されない: 他社に技術を知られるリスクがなく、回避技術を開発される心配もありません。
●保護期間が無期限: 秘密であり続ける限り、特許の最大有効期限である20年という期間に縛られず、半永久的にその優位性を保てる可能性があります。
●コストがかからない: 特許の出願や維持に関する費用が一切かかりません。
【デメリット】
●他者が独自に開発したら止められない: もし他社が、偶然まったく同じ製法を自力で開発した場合、それを止める術はありません。
●他社に特許を取られてしまうリスク: さらに、その独自開発した他社が特許を取得してしまうと、逆に自分たちがその製法を使えなくなるという最悪の事態も起こり得ます。
●情報漏洩のリスク: 社員の退職による技術流出など、秘密を「守り続ける」こと自体に多大な管理コストと困難が伴います。
どちらを選ぶべきか?
『わさビーズ®』の場合、その見た目から製造方法がある程度推測されやすい(リバースエンジニアリングされやすい)可能性を考慮し、技術を公開してでも強力な独占権で模倣を防ぐ「特許化」のメリットを重視したのではないか、と個人的には考えています。ただ、企業が置かれている状況や様々な状況・背景によりどちらの選択肢を取るかは変わってきますので一概にどちらが良いとは言い切れません。
まとめ:この事例から学べたポイント
この『わさビーズ®』の事例で、
●発明の捉え方: 特許の対象は、目に見える「モノ」に限らない。その製造プロセスである「方法」も、他社と差別化できる要素があれば、強力な知的財産となり得る。
●審査プロセスへの理解: 「拒絶理由通知」が来ても焦らない。権利化の落としどころを探るための重要なステップと捉え、冷静に対応する。
●「特許」か「ノウハウ」かの戦略的選択: 開発した技術を公開して権利で守るか、秘密にして守るか。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の技術や事業環境に合った戦略を選ぶことが極めて重要。
ということを学びました。
特許という公開されている情報から、
企業の考えや製品の戦略などを垣間見ることができるのは大変興味深いなーと感じました。
私が知らないだけで、家の中にある食材や様々な製品に特許を取得した製造方法で作られているものがたくさんあるはずです。日常の生活の中でまたこういったものを見つけたらブログの記事にしていきたいと思います。
ちなみに、田丸屋本店さんは今回紹介した『わさビーズ』に加え、他にも『ラー油ビーズ』『ゆずビーズ』、その他さまざまなわさび食品を取り扱っておられますので、是非ご興味がある方はHPをチェックしてみてください!