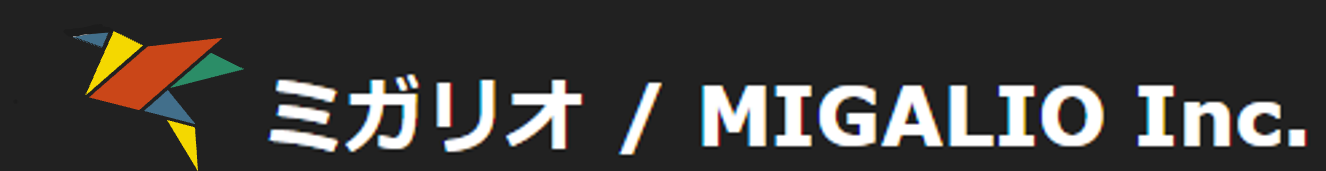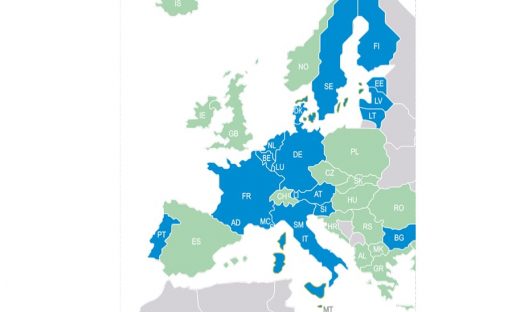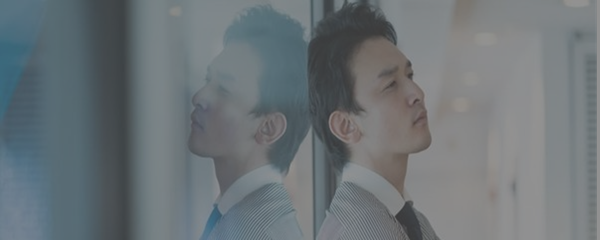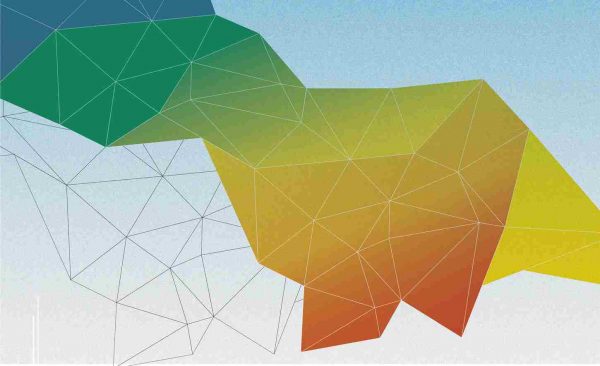【おでかけ×知財】水族館の水槽に関する特許

あたたかい日があったと思ったら、
急激に寒くなって雪がちらつく日もあったり。
そんなまさに三寒四温のこの季節。
家族で水族館へ行ってきました!
4最になった息子もなんだか最近は体調を崩し気味だったのですが、
やっと体調が回復したため、休日を利用して久しぶりに
家族で水族館へお出かけをしました。
日本最大級のムサシトミヨや貴重な食虫植物ムジナモが見られる
淡水魚専門の珍しい水族館です。自然豊かな公園内にあり、水族館の他にも
アスレチックやバーベキューも楽しめる、家族連れにぴったりのスポットです!
噂ですが、あのさかなクンさんも時々訪れるとか…
子供も魚に興味深々で楽しく館内を見て回ったのですが、
ふと思ったのが、「この水槽はどうやって掃除しているんだろう」ということ。
そして、「それにまつわる特許ってあるのかな?」とも。
調べてみたら、ある企業さんの水槽の清掃に関しての特許を
見つけましたので今回は記事にしてみたいと思います。
水族館の水槽にまつわる特許とは?
特許を保有している会社のお名前は、「日本サカス株式会社」さん
※日本サカスさんの公式HPはコチラ
ワンストップで全て取組む、日本でも珍しいトータルプロデュース企業です。
製品が使われている場所として、水族館はもちろんのこと、個人のお家、レストラン、
市場の水産設備に至るまでその幅広さは唯一無二といえるかもしれません。
特許についての概要
そして、日本サカスさんが保有している特許の一つが、
「水槽壁面研磨装置及び水槽壁面研磨方法」
※発明の名前をクリックすると、J-Platpatの情報にアクセスできます。
こちらの特許は、水族館などの大きな水槽の壁面を、
水を抜かずに研磨できる装置と方法に関するもの。
特許が解決する課題とは
特に大型の魚が展示されている大型水槽では、魚がぶつかることにより出来たアクリル壁面の傷や、
傷に入り込むように生えた藻などにより、透明度が低下してしまいます。
では、透明度が下がってしまったらどのようにするのか。
基本的には、ダイバーがスポンジなどで藻の藻を掃除することにはなりますが、
これでは出来た傷そのものを取り除くことはできません。
傷そのものを直すためには壁を研磨する必要があります。
そのためには、以下を実施しなければなりませんが、到底現実的とは思えません。
●水槽から水を全部抜く
●すべての魚を移動させる(大型魚の場合特に困難)
●修理中は展示を閉鎖する
確かに、水族館に行くと水槽の壁に藻が生えてしまって
少し見づらくなっている水族館もたまにありますよね。
特許の特徴
●研磨室
箱状の研磨室があり、その一部が開口しています。
開口部が水槽の壁面に密着することで、作業時に水や粉塵が外に漏れないようになっています。
●研磨部材とエアモータ
研磨室の中に、壁面を研磨するための研磨部材が配置されています。
研磨部材は、空気圧で動くエアモータによって回転し、壁面の傷を削ります。
●水密シール
研磨室の開口部には弾性のある水密シールがあり、
壁面としっかり密着することで水の侵入を防ぎます。
●粉塵の吸引機能
研磨によって生じた粉塵は、研磨室内で水とともに吸引され、
外部に漏れない仕組みになっています。これにより、研磨中でも
水槽内の生物に悪影響を与えることなく作業が可能です。
使用方法
●ダイバーが装置を水槽壁面に押し当て、密閉された研磨室を作る
●水ポンプが研磨室内に吸引力を生み出す
●エアモーターが研磨部材を回転させ、壁面を研磨する
●研磨中に発生した粉塵は水と一緒に吸引口から排出される
●水は水槽外でろ過され、水槽に戻される
●ダイバーは装置を壁面に沿って移動させる
この特許のメリット
●水族館は水槽から水を抜くことなく、営業を止めずに傷がついた壁面を研磨可能
●大型魚を移動させる必要がない
●研磨中も水質と魚の健康を維持できる
●水中世界の元の透明な視界を回復させることができ、来場者の満足度が高まる。
まさに画期的な発明及び特許ですよね!!
日本サカスさんのHPの導入実績のページを見ると、
有名な水族館や、全国の水族館での施工実績があるようです。
もしかすると、皆さんが行かれたことのある水族館もあるかもしれません。
特許の新規性喪失の例外とは
ちなみに、この特許の情報を見てみると、
新規性喪失の例外の表示という項目が書誌情報の中に書かれています。
特許が有効となる条件
特許が有効に成立するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります:
●新規性:その発明が世の中に存在していないこと
●進歩性:その発明が既存のものと比べて「ちょっと工夫した」程度ではなく、
本当に創造的であること
●産業上の利用可能性:その発明が実際に産業で使えること
特に重要なのが「新規性」です。
一般的に、発明を公開してしまうと、その時点で「世の中に存在する」ものとなり、
特許の新規性が失われてしまい、特許として成立しなくなります。
新規性喪失のよくあるケース
例えば、次のような状況を想像してみてください:
来場者から大絶賛され、自信を持って特許出願しようとしたところ、
「既に公開済みなので新規性がない」と言われてしまいました。
これが「新規性喪失」の典型的なケースです。発明を公開してしまうと、その時点で世界中の誰もが知り得る状態になり、もはや「新しい」とは言えなくなります。
では、新規性が喪失された場合は絶対に特許を取得することができないのか。
そうではありません。
新規性喪失の例外の条件
以下の条件を満たせば、例外的に発明の新規性は失われなかったものとして取り扱われる可能性があります。
●特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が公開されたケースに該当すること。
●発明が公開された日から1年以内に特許出願をすること。
●特許出願時に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること。
●特許出願の日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること。
実際に今回の出願では、以下のような内容で新規性喪失の例外について記載されています。
新規性喪失の例外に関しての詳しい情報に関しては、
以下特許庁サイトをご確認ください。
「特許庁:発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html
まとめ
水族館の水槽のお掃除方法に関しての今回の特許。
水族館へおでかけしたことがきっかけになって今回このような記事を書きましたが、
普段からアンテナを高く張り、「どんな技術が使われているのだろうか」
「もしかすると特許が使われているのではないか」といった目線で、
日常生活を送ればもっともっとたくさんのことに気づき、学べるかもしれません。
不定期にはなりますが、今後もどんどん発信をしていこうと思います。