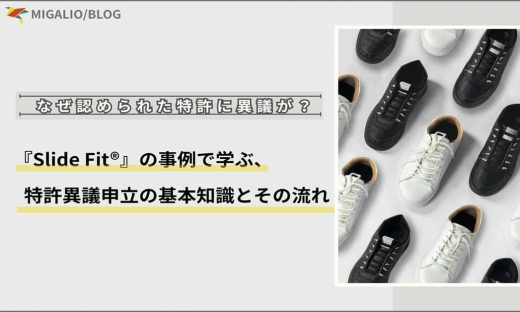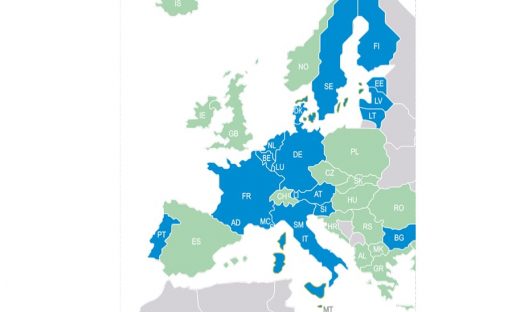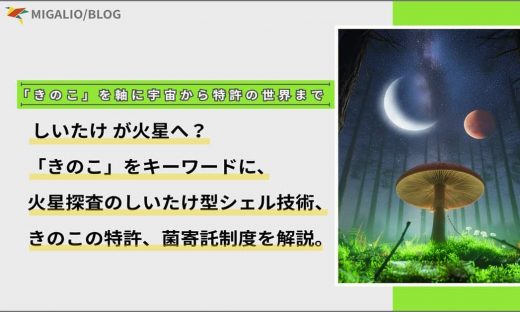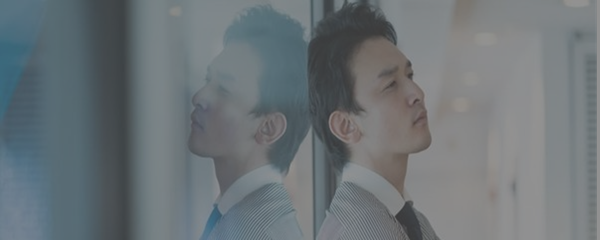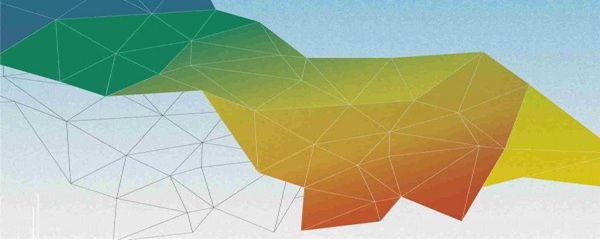国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しについて

少し前になりますが、特許庁HPのお知らせにこのようなページがアップされていました。
産業構造審議会知的財産分科会 第54回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧
(出典元:特許庁HP)
そのページに添付されていた資料を開くと、
6ページ目に「4.国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直し」という項目がありました。
そこで今回の記事では、
・資料に書かれていた内容のまとめ
・(上記の通りに見直しが行われた場合)企業知財部さんにどのような影響が出そうか
の2点について書いていきたいと思います。
※※※前提として、上記の見直し事項に関してはまだ検討段階であり、
「現行のルールが変わることが確定しているわけではない」です。予めご理解ください。※※※
資料に書かれていた内容のまとめ
国内優先権制度の昔と今
●国内優先権制度とは
国内優先権制度とは、最初に出した特許出願(先の出願)の内容を基に、
1年以内に改良版の特許出願(後の出願)を出せる制度です。
後の出願は、先の出願の日付で優先権を主張できるため、
その間に他の人が似たような発明を出願しても、自分の方が先だと主張できるという制度。
●導入当時(1985年)の狙い
問題:今よりも特許審査に時間がかかりすぎていた。
解決策:同じような内容を二重に審査してしまうことによる時間的な負担を軽減するために、
後の出願が公開される前に先の出願を自動的に取り下げる(みなし取下げ)ことにした。
●現在起きている問題
①権利取得の予測が困難
昔:審査が遅かったので、先の出願が権利になるかどうか予測しやすかった
今:審査が早くなったため、先の出願がいつ権利になるか、それとも取り下げられるかが分からない
結果:出願人が権利を取れるかどうか予測できず、混乱が生じている
②特許庁の業務負担増加
出願人への確認作業が増えた
システムの複雑化により運用コストが増加
③国際出願との相性が悪い
PCT国際出願(世界各国に一度に出願できる制度)と組み合わせると、処理が複雑になる
将来的な電子化(ePCT)にも対応しにくい
日本独自の制度のため、国際的な調和が取れていない
●要するに何が課題か
1985年に作られたこの制度は、当時の「審査が遅い」という状況に合わせて設計されたが、
現在は審査が早くなり、国際化も進んだため、この制度が逆に負担を生む原因となっている。
したがって、制度の見直しが必要だと認識されており、議題や検討事項の1つとしてあがっている。
起きている課題を解決するための見直し案について
現在:国内優先権を使った場合、先の出願は1年4月後に自動的に取り下げ
↓
変更後:先の出願も通常の出願と同じ扱いにして、出願から3年以内に審査請求しなければ取り下げ
つまり、先の出願の生存期間を「1年4月」から「最大3年」に延長する提案が出ている。
この提案に対しての賛成意見としては、
・企業の柔軟性向上:
一度「権利化不要」と判断しても、事業方針が変わって後から権利化したくなる場合がある
・選択肢の拡大:先の出願が3年間残っていると、状況に応じて権利化を選択できて助かる
反対意見としては、
・システム対応負担:各企業の特許管理システムの変更が必要
・監視業務の増加:第三者の立場として監視すべき出願数が増える
・慎重な検討要求:ユーザーの意見をもっと確認してから進めてほしい
などがあげられている。
(上記の通りに見直しが行われた場合)
企業知財部さんにどのような影響が出そうか
対応しなければならない点・大変な点
<案件管理の複雑化>
・監視期間の延長:先の出願を最大3年間管理する必要(現在は1年4月)
・データベース管理負担:より多くの出願を長期間追跡する必要
・期限管理の複雑化:異なる期限(審査請求期限、優先権期限等)の並行管理
<コスト負担の増加>
・維持管理費用:長期間の案件管理に伴う運用コスト増
・人的リソース:より多くの案件を処理するための人員・時間
<競合他社監視の負担増>
・監視対象の増加:他社の先の出願も3年間監視対象として残る
・分析工数の増加:より多くの出願状況を継続的にチェック
・情報収集コスト:長期間にわたる市場動向の把握
<判断業務の複雑化>
・権利化判断の複雑化:3年間の事業変化を考慮した権利化戦略の検討
・ポートフォリオ管理:先の出願と後の出願の両方を考慮した全体最適化
・予算管理の複雑化:長期間にわたる審査請求費用の予算計画
制度が変わることで得られるメリット
<戦略的柔軟性の向上>
権利化判断の猶予:事業方針変更に応じた権利化判断が可能
リスクヘッジ:後の出願が拒絶された場合の先の出願による救済機会
投資判断の余裕:市場状況を見極めてからの権利化判断
<時間的余裕の確保>
・審査請求判断時間:3年間かけてじっくり権利化を検討可能
・事業化準備期間:発明の商業化状況を見極める時間的余裕
・競合分析時間:他社動向を十分に分析してからの判断
<権利活用機会の拡大>
・ライセンス機会:長期間保持により、ライセンス交渉の機会増加
・防衛特許活用:競合対策としての権利保持期間延長
・M&A対応:企業買収等での知財価値向上
<リスク軽減効果>
・権利取得機会の確保:早期の取下げによる権利喪失リスクの回避
・訴訟対応余裕:競合他社との紛争に備えた権利保持
・技術トレンド対応:技術動向の変化に応じた柔軟な対応
まとめ
現行の制度に対して課題感を持っている人、持っていない人、見直しを求める人・求めない人
など所属する会社や業務の在り方などにより想いや価値観も様々だと思います。
今回、想定される企業知財部さんへの影響もまとめましたが、
全ての企業、全ての知財部さんにあてはまるわけではないと思います。
ただ、こういった制度の見直しの潮流があることを理解して、
自身の業務が「こう変わるかもしれない」「こう変わったらこのように動かなければいけない」
などの想定をして、身構えておくことはとても大切なことなのではないか、と感じました。
それは、知財部さんだけに限った話ではなくどの仕事、業界にもいえることだと思います。
自戒の意味も込めて。