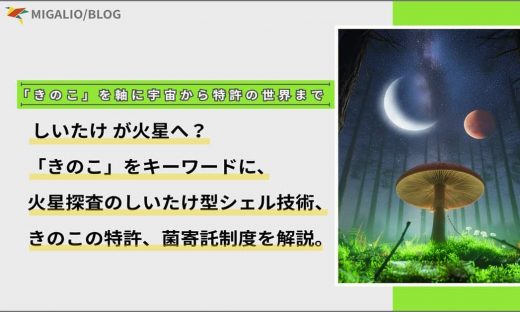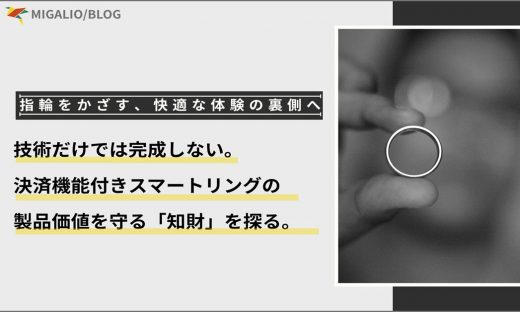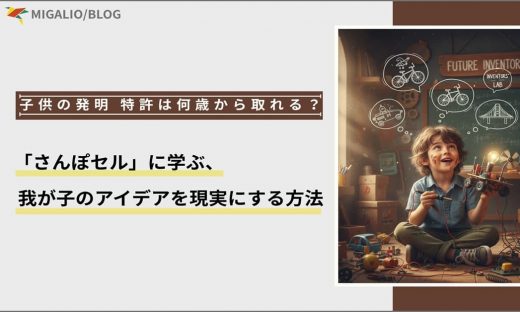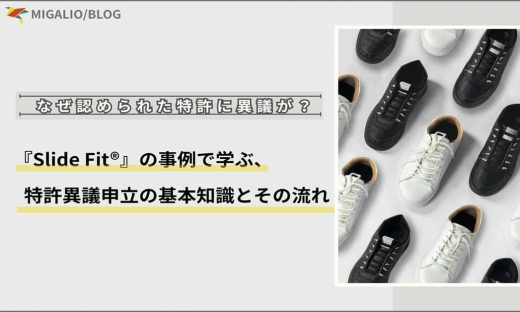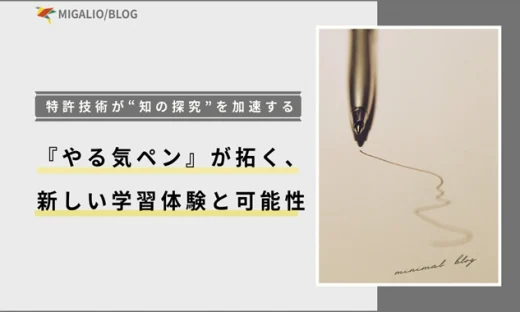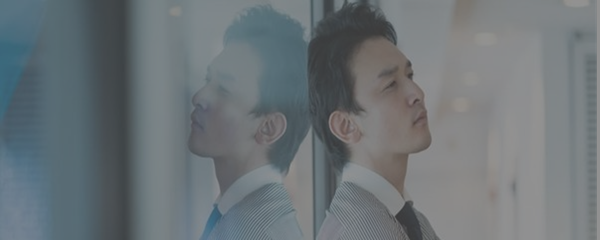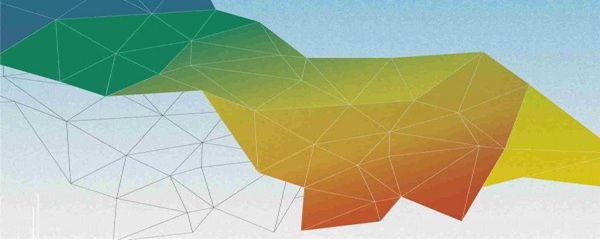平山甚太の米国特許から現代花火の特許まで。秋花火の夜空に想う。知財で読み解く花火の進化。「玉名」や「花火師」も知ることで、花火鑑賞が更に楽しく、深くなる。
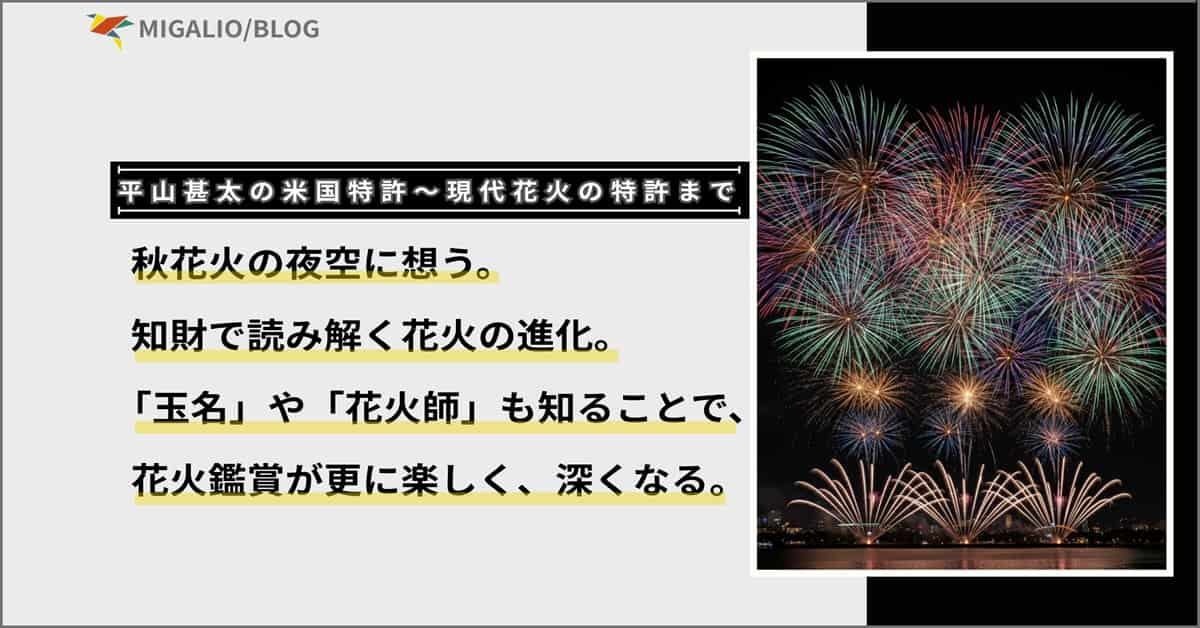
休日見たニュースで初めて聞いた「秋花火」という言葉。なんでも最近では、空気が澄んで、花火本来の鮮やかな色彩が楽しめるため「秋」に花火大会を行うことが増えてきているとか。確かに、例年の夏の暑さを考えるとたとえ夜でも、熱中症の危険もありますし、過ごしやすい秋に行うことはとても良いかもしれません。夏の風物詩=花火もいつしか、秋の風物詩へ…みたいなことも有り得るのかな…なんてことを考えました。(参考)
夜空を彩る、あの息をのむような一瞬の芸術。今回は、「花火」にまつわる特許を紹介しつつ、その歴史と花火を更に楽しく・深く楽しむための豆知識的なものを記事にしてみたいと思います。調べてみると、いろいろと面白いことが分かってきました。江戸時代から続く花火師たちの情熱と、その技術を守り伝えるための「技術革新」の昔と今に迫っていきたいと思います
日本初の特許より早かった「アメリカの花火特許」
日本の特許制度はいつ始まったかご存知でしょうか?
実は、日本で最初の特許法が施行されたのは1885年(明治18年)のことです。
しかし、それよりも早く「花火」に関する特許を海外で取得した日本人がいました。それが、花火師の平山甚太(ひらやま じんた)です。(参考)
日本初の特許よりも早く、日本人がアメリカで特許を取得していた…これってすごいことです!!
【コラム】日本人が初めて取得した米国特許「昼花火」とは?
平山甚太は、日本の特許制度が始まる2年前の1883年(明治16年)、アメリカで「昼花火(Daylight Fireworks)」に関する特許を取得しました。これが、記録に残る「日本人が取得した初の米国特許」です。
では、その「昼花火」とはどのようなものだったのでしょうか?
それは、夜に光で魅せる花火とは全く異なり、日中に打ち上げる花火でした。その内容は、筒で打ち上げた玉が上空で開くと、中からパラシュート(落下傘)をつけた人形や旗、万国旗などが飛び出してくるという、エンターテインメント性の高いものだったと言われています。
日本の制度が整う前から、自らの独創的なアイデアを「権利」として守るために海外に目を向けた平山甚太。その先見の明には驚かされます。
【関連記事】
ちなみに、日本国内での「日本初の特許」はどのようなものだったのでしょうか? 日本の技術革新の原点ともいえる「日本初の特許」や「世界初の特許」については、発明の日にちなんだ内容のこちらの記事に出てきますので是非見てみてください。
江戸から続く技術革新:「鍵屋」と「玉屋」
平山甚太が海外で特許を取得するほどの高い技術。その原点は、江戸時代にまで遡ります。
日本の花火文化が大きく花開いたきっかけの一つが、1733年の「両国の川開き」でした。 当時、花火を担当したのが「鍵屋」です。(参考)
その後、鍵屋からのれん分けする形で「玉屋」が誕生。両国の川を挟んで二大花火師がその技を競い合ったことで、日本独自の世界に誇る「丸い花火」の技術などが磨かれていったのです。 この「競争」こそが、日本の花火技術を世界レベルに押し上げた原点なのではないでしょうか。
打ち上げ花火を支える「現代の特許」たち
江戸時代の職人たちが「技」で競い合ったように、現代の花火師たちも、その技術を「特許」という形で守り、日々革新を続けています。ここでは「へぇ~」と思える、現代の打ち上げ花火を支える4つの特許をご紹介します。
①【花火×AI】花火師の「匠の技」を学習するAIシミュレーター特許
(特許第7582661号)
1つめは、まさに現代的、花火師の「経験と勘」をAIで学習・支援するシステムに関する発明です。
【特許が解決する「課題」の背景は?】
花火開発の難しさは、その「再現性の低さ」にあります。新しい花火を開発するには、職人の長年の経験と勘が頼りです。知識は師匠から弟子へと感覚的に伝えられることが多く、試作品を作って打ち上げてみないと、狙い通りの形や色になるかが分かりません。これでは開発にも知識の習得にも膨大な時間とコストがかかってしまいます。
そこでこの発明は、AI(機械学習モデル)を使った「花火開発支援装置」を提案しています。このAIには、過去の膨大な「花火玉の設計図(実在構成情報)」と「それが実際に開花した映像(実在開花情報)」をセットで「教師データ」として学習させてあります。
このAIができることは、驚きの2種類です。
- パターンA(順方向の予測)
花火師が「こんな設計図で作ったらどうなる?」と花火玉の【構想構成情報】を入力すると、AIが「こんな風に開花しますよ」という【推定開花情報(シミュレーション)】を生成します。 - パターンB(逆方向の予測)
これが特にスゴイのですが、花火師が「夜空にこんな花を描きたい!」と理想の【構想開花情報】を入力すると、AIが「それなら、こんな設計図で作る必要があります」と【推定構成情報(設計図)】を逆算して生成してくれるのです。
熟練の花火師の「匠の技」をAIが学習・データ化し、若手でもシミュレーションや設計支援を受けられるようにする、まさに花火業界のDXと言える発明ですね。
②【花火×効率化】現場の悪夢「雨天中止」を救う特許(特許第6651671号)
2つめは、花火師さんの安全と効率を劇的に改善する、「カートリッジ式」の打ち上げ花火の発明です。
【特許が解決する「課題」の背景は?】
花火大会の現場では、数百本もの発射筒(つつ)が並びます。従来は、その一本一本に、花火師さんが「①発射用の火薬(むき出し)を設置し」「②花火玉を正しい向きで設置し」「③電気点火用の配線を行う」という作業を手作業で行っていました。これが非常に危険で時間がかかります。
最大の悪夢は「雨天中止」です。安全のため、設置した数百発の火工品を、今度は「むき出しの火薬」に注意しながら、すべて手作業で撤去しなくてはなりません。これは想像を絶する危険と労力がかかります。
そこでこの発明は、「打ち上げ花火用カートリッジ」を提案しました。
これは、あらかじめ工場で「①花火玉」「②発射火薬」「③導爆線(ヒューズ)」の全てが、安全な容器(カートリッジ)の中に完璧な状態でセットされた“オールインワン・パッケージ”です。
この発明が現場をどう変えるかというと…
- 設置が超カンタン!
花火師さんは、このカートリッジを発射筒に「ストン」と落とし入れ、配線をつなぐだけ。むき出しの火薬を触る必要がなく、迅速・容易・安全に設置が完了します。 - 撤去が超カンタン!
もし雨で中止になっても、発射筒からこのカートリッジを「スポン」と抜き出すだけ。火薬も花火玉も安全な容器に入ったままなので、撤去作業の危険性がゼロに近くなります。 - 輸送と保管面にも配慮!
このカートリッジ、輸送中に花火玉がガタガタ動かないよう「緩衝材(クッション)」が入っているだけでなく、なんと湿気から火薬を守るための「乾燥剤(シリカゲル)」まで内蔵しているんです。
③【花火×安全性】”電池”を無くして安全に!「ワイヤレス給電」点火特許
(特許第7218641号)
3つめは、花火大会の「誤作動」や「誤爆」のリスクを限りなくゼロに近づける、革新的な「無線点火システム」に関する発明です。
【特許が解決する「課題」の背景は?】
音楽と花火をシンクロさせる現代の花火大会では、遠隔操作での「電気点火」が必須です。しかし、従来の無線システムには大きな課題がありました。
それは、現場の各花火(点火ユニット)に「内蔵バッテリー(電池)」が必要だったことです。電池があると、点火待機中も常に電気が流れている状態になります。すると、他の電波との「混信」や、地面を流れる「迷走電流」を拾ってしまい、意図しないタイミングで花火が誤爆するという、最悪の事故につながる危険性がありました。
そこでこの発明は、「現場の点火ユニットから、”電池”を一切無くす」という驚きの方法を考え出しました。それが「ワイヤレス給電」技術の応用です。
このシステムの仕組みは、ざっくりと説明すると以下となります。
- ステップ①:現場は「ゼロ電力」
準備段階では、現場に並べられた数百発の花火(無線式点火ユニット)には一切電力がありません。電池が無いので、混信や迷走電流による誤爆は物理的に不可能です。 - ステップ②:点火”直前”に「ワイヤレス給電」
安全な遠隔操作室から、花火を打ち上げる”直前”にだけ、操作アンテナを通じて「駆動用エネルギー(電力)」を無線で送ります。 - ステップ③:「その場で充電」して点火!
電力(駆動用エネルギー)を受け取った現場の点火ユニットは、内蔵された「蓄電部(コンデンサ)」に“その場で”電気を溜め、点火準備が完了したことを無線で返信。操作室が「点火!」という制御信号を送ると、溜めた電気を使って安全に花火を打ち上げます。
「点火する瞬間」以外は現場の電力をゼロにするという、まさにコロンブスの卵的発想。より安全に花火を楽しめるようになる発明です。
④【花火×未来】AIが音楽を”聴いて”花火とドローンを自動演出する特許
(特許第7538562号)
最後の4つめは、花火大会の「未来の姿」を予感させる、AI・ドローン・花火を完全自動で同期させるエンターテインメント・システムの発明です。
【特許が解決する「課題」の背景は?】
近年、花火大会でドローンを使った光のショーが組み合わされることが増えました。(国内の花火大会で初となる花火搭載ドローンを用いた500機のドローンショーを実施『第22回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会ドローンショー』 株式会社レッドクリフ)しかし、従来の方法では、ドローンの動き、ドローンの発光、音楽、そして花火の打ち上げタイミング…これら全てを、人間が「手作業」で1秒1秒プログラムしていました。
これでは、新しいショーを1つ作るのに膨大な手間と時間がかかりますし、毎回似たような演出になりがち、という課題がありました。
そこでこの発明は、「AIショー・ディレクター」とも呼べる装置を提案しています。
この装置は、あらかじめ「(A)飛行パターンのデータベース」「(B)発光パターンのデータベース」「(C)花火の打ち上げパターンのデータベース」を持っています。そして、AIが音楽の「特徴(リズム、テンポ、ビート、周波数など)」と、これらのABCの各パターンをどう連携させれば感動的かを学習しています。
この発明がスゴイのは、ここからです。
- イベント主催者が「新しいショーを作りたい」と思ったら、AIに「新しい音楽(音情報)」を入力するだけ。
- AIは、その音楽を「聴いて」自動で解析します。
- そして、曲の盛り上がりに合わせて「(A)ドローンの動き」「(B)ドローンの光」「(C)花火の打ち上げ」を完璧に同期させた、全く新しい演出パターンを”自動で生成”してくれるのです。
つまり、人間がゼロからプログラムを組むのではなく、AIが音楽を解釈して最適な「ドローン×花火ショー」を自動で振り付けてくれる技術です。これぞまさに、未来の花火演出です。
特許だけじゃない!秋花火を深く楽しむ「玉名」と「花火師」の世界
最先端の特許技術を知ると、花火の「技」そのものにも興味が湧いてきませんか?
ここでは、花火鑑賞がもっと面白くなる「玉名」と「花火師」の世界をご紹介します。
【コラム】玉名を読めば花火の始まりと終わりまで全て分かる。「玉名(ぎょくめい)」の読み解き方
花火の世界には、特許とはまた違う、伝統的な「知財」の守り方が存在します。それが、花火大会のプログラムに載っている「玉名(ぎょくめい)」です。
玉名(ぎょくめい)とは、その花火(作品)に付けられる「銘」のことで、いわば花火玉の“履歴書”や“設計図”のようなもの。花火師の独創性や技術がこの名前に凝縮されています。(参考)
例えば「昇曲導付(のぼりきょくどうつき) 五重芯(ごじゅうしん) 変化菊(へんかぎく)」という玉名は、以下のような要素で構成されています。
- 昇曲導付:花火玉が「昇(のぼ)」っていく途中で、「曲導(きょくどう)」(小さな花火)を放出する仕掛けが「付」いていること。
- 五重芯:花火玉の中心構造が「五重」の「芯」になっていること。円が五重に開く、非常に高度な技術です。
- 変化菊:「菊」(星が尾を引く花火)であり、さらにその色が途中で「変化」すること。
このように、玉名を見れば「いつ」「どのような現象が」「どんな構造で」「どう変化するか」が分かるようになっており、花火師の技術とプライドが示されているのです。
現代に受け継がれる「技」:日本の有名花火会社
江戸時代の「鍵屋」「玉屋」の競争が技術を発展させたように、現代でも多くの花火会社(花火師)がその技を競い合っています。ここでは、数々の競技大会で名を馳せる、代表的な花火会社をご紹介します。ここに書いてある以外にもたくさんの花火師(会社)が日々その技術を磨いていますので、気になった方は是非他の花火師さんも是非調べてみてください!
- 野村花火工業(茨城県)
明治8年創業。社長の野村陽一氏は「プロフェッショナル仕事の流儀」でも特集された有名花火師です。かつて未踏の時代に「五重芯」を完成させたことで一躍有名になりました。「野村ブルー」と評される独特の青色や、「幻想イルミネーション」に代表されるグラデーション系の新作花火が特徴で、大曲や土浦の競技大会では内閣総理大臣賞を多数受賞しています。(参考) - 山﨑煙火製造所(茨城県)
明治36年創業。伝統的な割物花火の技術力は日本有数とされ、高難易度とされる四重芯・五重芯にも積極的に挑戦しています。代名詞は「銀点滅」で、独特のすっきりとした銀の発色と点滅のキレ味は随一と評されています。近年は「五化牡丹」など、独特の色変化を持つ星づくりにもチャレンジしています。(参考) - 紅屋青木煙火店(長野県)
大正5年創業。初代の青木儀作氏は「多重芯割物花火」の技術完成の功績で黄綬褒章を受章しています。伝統的な割物花火の高い技術を継承しつつ、音と光を厳密にシンクロさせる「ミュージック花火」にも力を入れており、国内外で高い評価を得ています。全国花火競技大会「大曲の花火」では内閣総理大臣賞を2度受賞しています。(参考)
まとめ:花火の「裏側」を知って、いつもの花火鑑賞をより深く楽しんでみましょう!
今回は、秋花火をきっかけに、日本の花火を支える技術と知財の世界をご紹介しました。
ただ「きれいだな」と眺めるだけでなく、
- 花火大会のプログラムを手に取り、「玉名(ぎょくめい)」からその花火の構造や仕掛けを想像してみる。
- 「これは野村花火工業の“野村ブルー”かも」「このミュージック花火は紅屋青木煙火店かな?」と、花火師(会社)ごとの個性に注目してみる。
- そして、平山甚太が米国特許を取得した時代から、現代の特許に至るまで、花火師たちの「技術」と「知財」への情熱に思いを馳せてみる。
そんな新しい視点を持つだけで、いつもの花火大会が、より深く、何倍も面白い、あなたの心に残るエンターテインメントになるはずです。
次にあなたが夜空を見上げるとき。その一瞬の輝きの裏にある物語と共に、花火鑑賞をアップデートしてみてはいかがでしょうか。