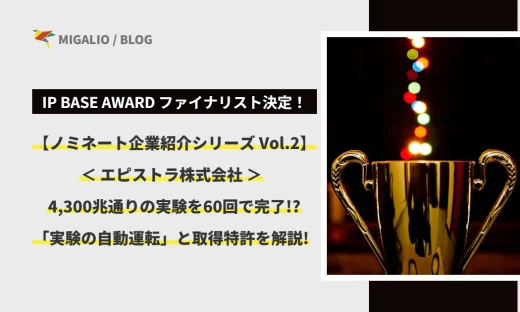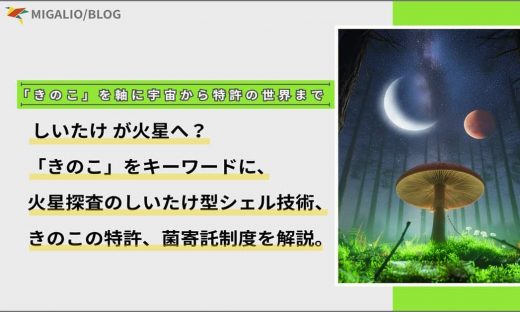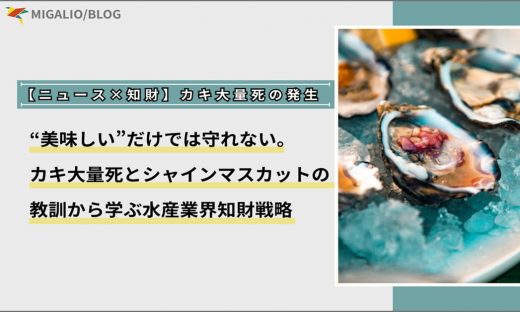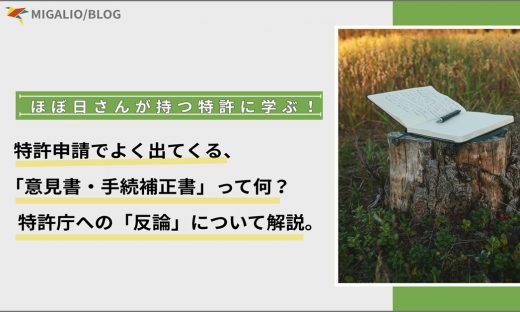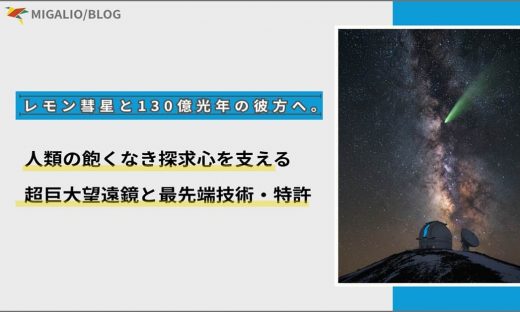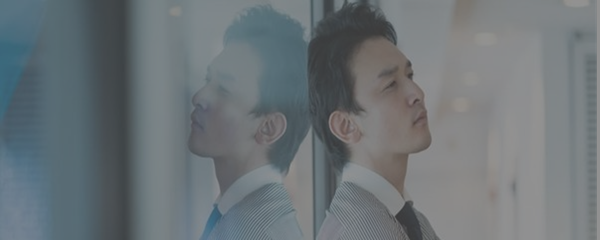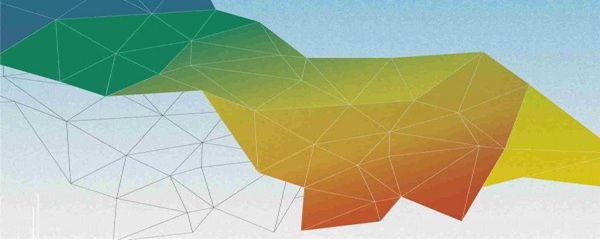米国の特許制度、歴史的な転換点か。
価値に基づく新手数料案が日本企業に与える影響
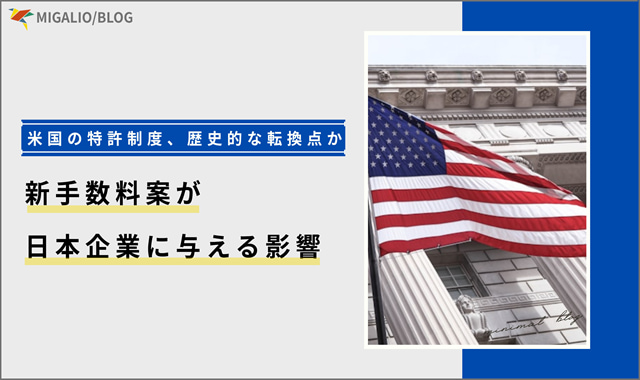
はじめに:米国の知財制度に歴史的な変革の可能性
米国の知的財産制度が、大きな変革の可能性に直面しています。
先日、米ウォール・ストリート・ジャーナルは、米商務省が現行の定額制の特許手数料とは別に、
特許の経済的価値に基づいて新たな手数料を課す案を検討していると報じました。
『米政権、特許の新手数料検討 歳入増を狙う』
掲載元:THE WALL STREET JOURNAL 2025/7/29
『米の特許制度見直し、実現すれば三星やLGなど韓国企業の手数料が9.9倍に』
掲載元:東亜日報 2025/8/6
この改革案は、200年以上にわたり世界のイノベーションを牽引してきた
米国の特許制度の根幹に関わるものであり、もし実現すれば、
AppleやGoogleといった巨大テック企業はもちろん、
米国で多くの特許を保有する日本企業にも多大な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、この新たな制度改革案の概要と、その背景にある米国の特許制度の仕組み、
そして今後のビジネスやイノベーションにどのような影響が考えられるのかを、
噛み砕いて分かりやすく解説していきます。
米国の特許制度とは?基本的な役割と仕組みの確認
今回の改革案を理解するために、
まずは米国の特許制度の基本的な役割と仕組みについて確認しておきましょう。
特許制度には、主に二つの重要な役割があります。
- 発明者へのインセンティブ付与:
新しい技術やアイデアを「発明」した人に対し、一定期間その発明を独占的に使用できる権利(特許権)を与えます。これにより、発明者は安心して投資を回収し、利益を得ることができ、さらなる発明への意欲が湧きます。 - 社会全体の技術進歩への貢献:
特許権を与える代わりに、その発明の内容は社会に公開されます。これにより、他の研究者や企業がその技術を参考に、新たな改良や別の発明を生み出すことが可能になり、社会全体の技術水準が向上します。
この仕組みを維持するため、特許権者は米国特許商標庁(USPTO)に対し、定期的に「維持手数料(メンテナンスフィー)」を支払う必要があります。現在の制度では、この手数料は特許の価値に関わらず、登録後の年数に応じて定められた「定額制」となっています。この安定した制度が、これまで米国の経済とイノベーションを支える基盤の一つとなってきました。
新手数料案の核心:「特許の価値」に基づく制度へ
今回報じられた改革案の核心は、この「定額制」から
「従価制(価値に応じる制度)」への転換、あるいは追加です。
報道によれば、商務省は特許権者に対し、特許の全価値の1%から最大5%に相当する手数料を
毎年課す案を検討しているとのことです。
これを身近な例に置き換えると、不動産に課される「固定資産税」の考え方に近いと言えます。
土地や建物の評価額に応じて税額が変わるように、特許が生み出すと想定される経済的価値に応じて、手数料の額が変動する仕組みです。
例えば、世界中のスマートフォンに使われるような基幹技術の特許や、画期的な医薬品の特許など、極めて価値の高い特許を保有する企業は、現在とは比較にならないほど高額な手数料を支払うことになる可能性があります。この改革の主な目的は、政府の歳入を数十億ドル規模で増加させることにあると見られています。
改革案がもたらす多角的な論点と影響
この改革案に対しては、当然ながら様々な方面から期待と懸念の声が上がっています。
主な論点を整理してみましょう。
論点1:イノベーションへの影響
産業界から最も強く懸念されているのが、イノベーションへの「ブレーキ」となりかねない点です。毎年高額な手数料が発生するとなれば、企業はリスクの高い長期的な研究開発をためらうようになるかもしれません。特に、資金力に乏しいスタートアップや大学、個人の発明家にとっては、特許の取得・維持が困難になり、新たな挑戦を阻害する要因となる可能性があります。
論点2:課税の公平性をめぐる議論
企業は、特許を活用して得た利益に対し、すでに法人税などの形で税金を納めています。
そのため、特許の「価値」そのものにまで課金することは、事実上の「二重課税」にあたるのではないか、という強い批判もあるようです。
論点3:「価値」の評価という難題
制度を運用する上で最大の課題となるのが、「特許の価値を誰が、どのように客観的に評価するのか」という点です。未来の収益性を予測することは極めて難しく、評価基準が不明確な場合、政府による恣意的な運用への懸念も生じてしまいます。
論点4:国際的な整合性
米国は多くの国際特許条約に加盟しています。このような独自の高額な手数料制度が、
既存の国際的な枠組みと整合性が取れるのかも、今後検討していかなければならないでしょう。
今後の展望と日本企業が注視すべきこと
現時点では、この改革案はまだ検討段階にあり、その実現には米国議会での法改正など、
多くのハードルが存在します。そのため、すぐに制度が変わるわけではありません。
しかし、この議論は「知的財産」という無形資産の価値を国家財政にどう結びつけるかという、
未来の経済政策を占う重要な試金石と言えます。
米国で事業を展開し、多くの特許を保有する日本企業にとって、この動向は決して対岸の火事ではありません。今後の特許戦略(どの技術を出願し、どの特許を維持・放棄するか)の策定や、研究開発投資の意思決定に大きな影響を与えかねないからです。
この歴史的ともいえる制度改革の議論がどのように進展していくのか、
今後も注意深く見守る必要があると思います。