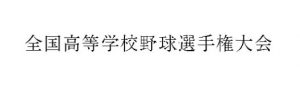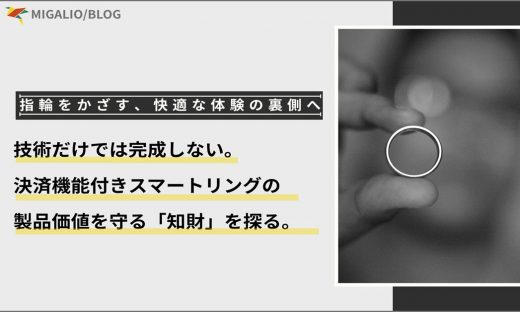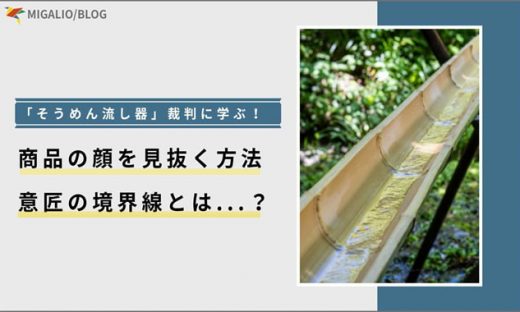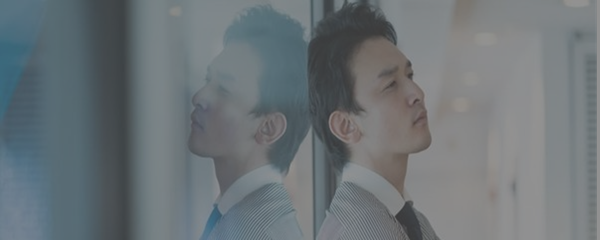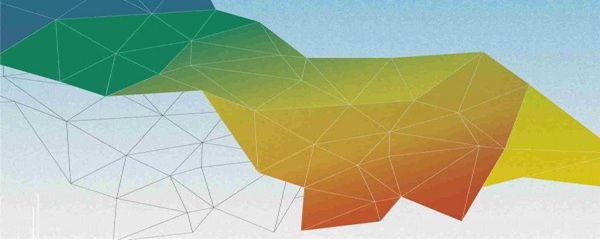知財の視点で見る甲子園
〇〇甲子園はアリ/ナシ?&スコアボードも商標!?
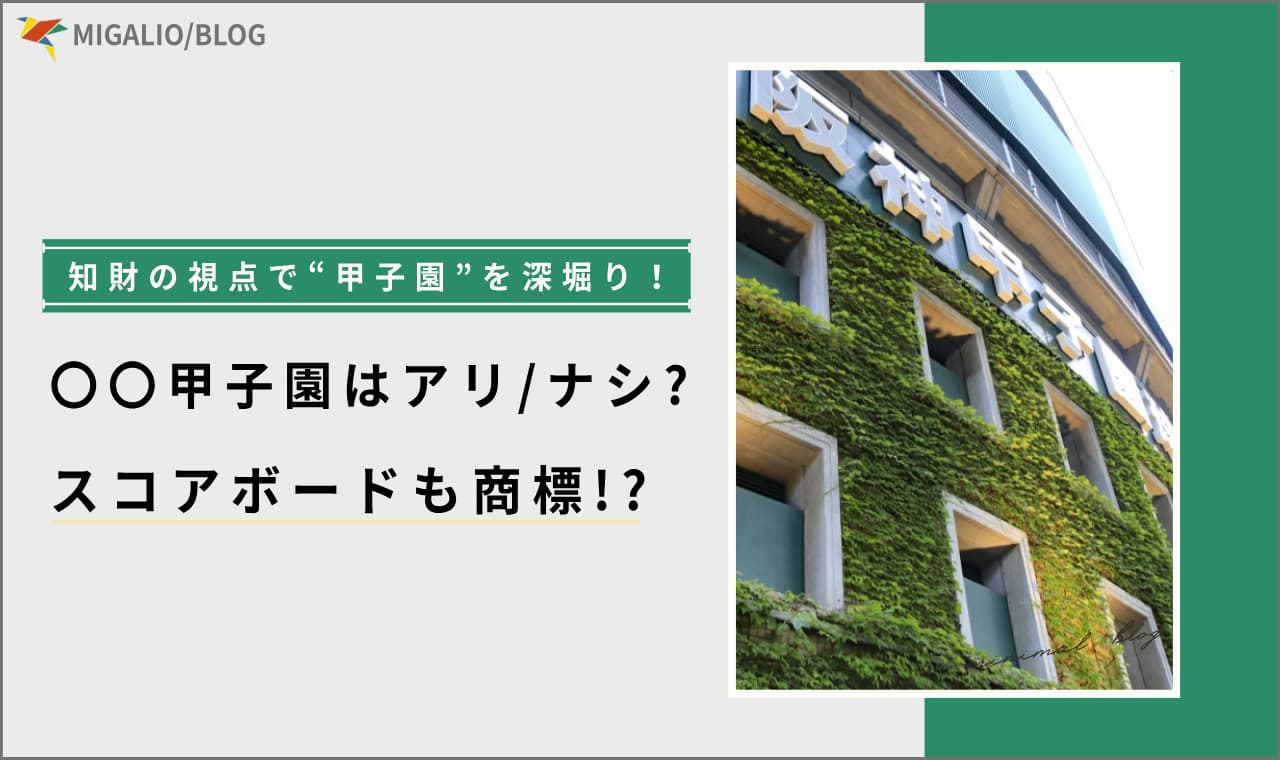
高校球児を見ると、なんだか応援したくなるのはなぜだろう
夏の風物詩といえば、多くの人が思い浮かべるのが「甲子園」ではないでしょうか。
高校球児たちの汗と涙が輝くあの場所は、私たちに毎年多くの感動を与えてくれます。
今年の甲子園では酷暑対策のため2部制が導入されました。
このブログを書いているお盆真っただ中本日8/15には第3回戦が行われ、決勝戦は8/23の予定です。
そんな「甲子園」をいつもと違って、知財の視点で深掘りしていこうと思います。
「甲子園」という言葉や、あの緑で覆われた凸のような形をした
象徴的なスコアボードに商標権があることはごご存知でしたか?
また、「『まんが甲子園』や『俳句甲子園』は商標権の侵害にあたらないの?」
「もし自分たちでイベントを企画するなら、『〇〇甲子園』って名前は使えないの?」
といった疑問にも今回の記事ではできるだけ分かりやすく答えていきたいと思います。
「甲子園」の商標権の所在について
「甲子園」関連の商標は、1つの団体が全てを所有しているわけではありません。
球場の名称としての「甲子園」
球場そのものの名称である「甲子園」や「阪神甲子園球場」の商標は、
球場を所有・運営する阪神電気鉄道株式会社が登録しています。
これは、第三者が勝手に「甲子園」を名乗る野球場を作ったり、
関連事業で名前を使ったりすることを防ぎ、ブランドイメージを守るためのものです。
大会の名称としての「全国高等学校野球選手権大会」
一方で、夏の高校野球大会の正式名称である「全国高等学校野球選手権大会」や、大会ロゴなどの商標は、主催者である朝日新聞社と日本高等学校野球連盟(高野連)が登録しています。
このように、私たちが普段「甲子園」と呼んでいるものは、
場所の名称と大会の通称という2つの側面があり、それぞれ権利者が異なるのです。
形まで商標に?甲子園の「スコアボード」が立体商標である理由
驚くべきことに、「甲子園」の商標は文字だけではありません。阪神甲子園球場の象徴ともいえる、あの緑色のスコアボードも、その形自体が「立体商標」として登録されています。
立体商標とは、商品や店舗の形状など、立体的なものを商標として認める制度です。
以前、こちらのブログでもエルメスの大ベストセラーである「バーキン」を題材に
立体商標の基本知識に関して記事にしました。
ご興味がある方は以下画像をクリックして是非読んでみてください!
では、なぜ甲子園のスコアボードが立体商標として認められたのでしょうか?
それは、長年の歴史の中で、あの独特なデザインのスコアボードが「阪神甲子園球場そのもの」を象徴する存在として、多くの人々に広く認識されるようになったからです。蔦の絡まる外壁とともに、あのバックスクリーン一体型のスコアボードは、単なる得点表示板ではなく、球場の顔としての強い識別力(他と区別できる力)を持っていると判断されたためだと思われます。
「〇〇甲子園」が商標権侵害にならない理由
さて、ここからが本題です。様々な権利者がいる中で、なぜ「まんが甲子園」や
「俳句甲子園」といったイベント名が問題にならないのでしょうか?
それは、商標権の効力が及ぶ範囲が限定されているためです。
阪神電気鉄道株式会社が持つ「甲子園」の商標は、その権利範囲が「野球の興行の企画・運営又は開催、野球場の提供」といった、主に野球に関連するサービスに定められています。
したがって、もし第三者が野球大会に「〇〇甲子園」と名付けて開催した場合、
権利者の事業と混同される可能性が非常に高く、商標権侵害となるおそれがあります。
一方で、「まんが甲子園」や「書道パフォーマンス甲子園」といったイベントは、
漫画や書道がテーマであり、登録されている「野球」というジャンル(役務)の範囲外です。
このように、提供されるサービス内容が全く異なるため、
原則として商標権の効力は及ばず、権利侵害にはあたらないのです。
加えて、「甲子園」という言葉が、長年の歴史の中で「高校生の全国大会における最高峰の舞台」といったイメージで社会に広く認識されている、という見方もあります。そうした背景から、野球以外の様々なジャンルにおいても、若者たちの目標となる大会の愛称として「〇〇甲子園」という名称が使われている、と考えることができるでしょう。
商標トラブルの事例:「観光甲子園」裁判の教訓
数ある「〇〇甲子園」という名前イベントの中には、過去に裁判まで行われたケースがありました。
今回はそのケースを紹介していきたいと思います。
そのイベントの名前は「観光甲子園」。
そのイベントの商標をめぐり、大学間で裁判にまで発展した事例がありました。
事件の概要
- 原告: 「観光甲子園」を商標登録し、イベントを開催してきた大学(A大学)
- 被告: 事業承継の候補として、A大学から引き継いで「観光甲子園」を開催しようと準備していた大学(B大学)
A大学は経営難から事業の承継先を探しており、B大学がその候補となっていました。A大学の担当者とB大学の間で話は進み、ロゴデータが送付されるなど、実務レベルでは引継ぎが行われていました。B大学は当然、正式な許諾があったものと信じてイベントの準備を進めていました。
ところが、A大学の内部で担当者から上層部への正式な報告・承認がなされていなかったため、
結果的にB大学の準備行為が「商標の無断使用」となってしまい、
A大学はB大学を商標権侵害で提訴したのです。
裁判所の判断
裁判所は、まず形式上は「B大学は正式な許諾なく商標を使用したため、
商標権侵害にあたり、過失があったと推定される」と判断しました。
しかし、ここからが重要なポイントです。判決は、結論として「B大学に過失はなかった」と判断し、損害賠償請求を認めませんでした。その理由は以下の通りです。
- B大学はA大学の事業承継先を探していると公式に聞かされていたこと。
- 引継ぎはA大学の事業中心人物との間で行われていたこと。
- 引継ぎ後、B大学が共催校となることが大会組織委員会で承認され、
対外的にも公表されていたこと。 - 実際にイベント用のロゴデータなどもA大学側からB大学に送付されていたこと。
この事例は、「〇〇甲子園」という名称を使用する際、たとえ担当者レベルで話が進んでいても、権利者(組織)としての正式な許諾を明確に確認することが、いかに重要であるかを教えてくれる貴重な教訓と言えるでしょう。今回は商標のお話でしたが、普通のビジネスの場においても認識の齟齬やコミュニケーション不足によって似たような事態に陥ってしまう可能性はあると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「甲子園」という一つの言葉を深掘りするだけで、商標権の奥深い世界が見えてきます。
- 「甲子園」関連の商標は、阪神電鉄(球場名)や朝日新聞・高野連(大会名)などがそれぞれ所有している。
- 球場のスコアボードも、その形が「立体商標」として登録されている。
- 多くの「〇〇甲子園」は、登録商標の権利範囲(野球関連)ではないため、問題になりにくい。
- しかし、「観光甲子園」の裁判事例のように、権利関係の確認を怠ると、思わぬトラブルに発展するリスクがある。
私たちの身の回りには、当たり前のように使っている言葉や目にしている形にも、実は様々な権利が関わっています。甲子園の熱戦を観戦する際には、そんな知的なウラ側にも思いを馳せてみると、また違った楽しみ方ができるかもしれません。
今年、深紅の優勝旗を手にするのはどの高校なのか。
私は開会前から今年は横浜高校が優勝するのでは?と予想しています。
【8/21追記】
昨日8/20、県立岐阜商との激戦の結果、横浜高校が敗退してしまいました…
今日は準決勝。どの高校が決勝戦に勝ち進むのか。